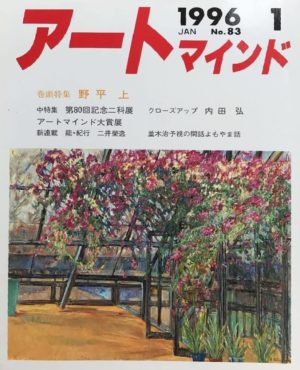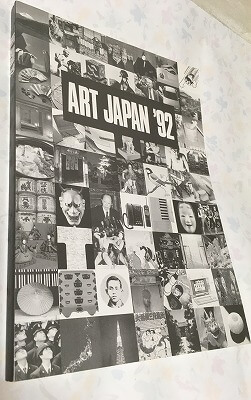浜口美和は筆者の母になりますが、この場をお借りして浜口美和の画家としての活動記録をまとめて置きたく存じます。
なお現在母は存命しておりますが、残念ながら2016年以降は頭の働きの低下により筆を握る意欲が沸かない状態が続いていますが、振り返ってみると「絵を描く」ことに人生の大半を捧げてきた母にとって、皮肉なことに今が一番穏やかな時間を過ごせているのではないか?と考えています。
画家になるまで
母は女4人男2人の兄弟姉妹の次女として埼玉県秩父町(現在の秩父市)に生まれました。
母の父は1901年の生まれで二十歳の頃から4、5年東京の本郷洋画研究所[1]で油絵を学なび、会社勤めをしながら水彩画家の小堀進氏[2]などに師事して1924年創立の白日会[3]に8回入選するなどの実績を残しています。
[1]Wikipedia「本郷洋画研究所」 https://ja.wikipedia.org/wiki/本郷洋画研究所
[2]Wikipedia「小堀進」 https://ja.wikipedia.org/wiki/小堀進
[3]白日会HP http://www.hakujitsu.com/
そのような父親の芸術的素養を受け継ぎ、長男は学校の美術の先生、三女はピアノ教室を開いていました。
母は父親と同じ絵を描く道に進むのですが、終戦後しばらくして高等女学校を卒業後は結婚するまで税務署で働いたことがあるような話を聞いた記憶がありますが定かではありません。
その後結婚をして東京にでてくることになるのですが、家には夫の両親が同居し、しばらくは絵を描くような状況ではなかったことと推察致します。
そのような中で2人のこどもを生み次男である筆者が小学校に通い始める年に初めて二紀展に出品をします。
ただ二紀展に出品を始めた時点では趣味でといいますか独学で絵を描いていた時期になります。
従いまして二紀展に出品したからといってすぐにプロの画家になれる訳でもなく、またそれまでに正式に絵を学んだ訳ではなく肩書が存在しないために、母は一念発起して武蔵野美術短期大学に通うことになります。30代で短大とは言え主婦をしながら大学に通うのはなかなか大変なことであったと思います。
それだけではなく、ある程度の貯金は有ったはずですが、片や主婦をしながら大学に通い、絵を描くための画材を購入するための費用も賄う必要があるため、自宅で絵画教室を開き近所の子供たちに絵を教えることでそれらの資金に充当していました。
そのような課題を克服しながら画家を目指していたため、美大卒業後すくに画家を目指す人に比べて一回りは年齢が上にであったことは否めません。
そのため年齢を正確に公にしないというか、年齢詐称というか実年齢よりも若いような振る舞いをして来たことは事実です。
そのような母の思いもあり下記の年譜でも年齢は明確化しておりませんのであらかじめご了承ください。
公募展初受賞は二紀展
| 年譜 | 1965年から1979年まで |
| 1930年代 | 埼玉県生まれ |
| 1965年 | 第20回二紀展初入選 ┗[~2011年まで47回連続出品] |
| 1969年 | 武蔵野美術短期大学美術科卒業 女流画家協会展初入選[~1978年まで毎年出品] 企画個展(於青山画廊) |
| 1972年 | 第26回二紀展【奨励賞】受賞 |
| 1973年 | 二紀展【同人】推挙 二紀選抜展出品 |
| 1974年 | 個展(於銀座) |
| 1975年 | 第4回現代洋画精鋭選抜展【銀賞】受賞 |
| 1976年 | 第30回女流画家協会展【クサカベ賞】受賞 スペイン美術賞展入選(於バルセロナ) |
| 1977年 | スイス美術賞展入選(於ジュネーブ) ┗[プチパレ美術館収蔵] |
| 1978年 | イタリア美術賞展入選(於ベネチア) 個展(於銀座) |
| 1979年 | ギリシャ美術賞展入選(於アテネ) 一枚の繪企画2人展(於銀座) 第1回花と女性美展入選(於そごう) |
[4]おかめ応援団「会社紹介」 http://okame-ouendan.com/html/company.html
なお出品は1回だけだったと思われますが、「花と女性」というのは二紀会創設者の一人である宮本三郎氏が取り組まれたテータだったので出品をしたのかもしれません。
30代後半で武蔵野美術短期大学を卒業することになりますが、卒業に際して制作した作品が「最優秀賞となり学校買い上げになった」と本人が書いた経歴書に記されています。
短大卒業と同時に、それまでは公募展は二紀展(10月)だけに出品していましたが、それに加えて女流画家協会展(5月末から6月始め)にも出品をします。
ただし女流画家協会展は1978年までは毎年出品をして1976年の第30回には「クサカベ賞」を受賞するのですが10回目を区切りとして辞めてしまいます。
女流画家協会展の詳細につきましては『浜口美和「女流画家協会展」出展作品集』をご参照いただければ幸いです。
また短大を卒業した1969年に初めての個展を表参道駅にほど近い青山画廊で開催しています。
やるからにはある程度売れる自信があったのだとは思いますが筆者が小学校5年の時の記憶にはなりますが「売れなくはなかったけれど」といった状況だった事を薄っすらと覚えています。
なお個展・グループ展の詳細は『浜口美和個展・グループ展等アーカイブ』にまとめていますのでご参照いただければ幸いです。
その後1972年に二紀展で人生で初めての賞となる「奨励賞」を受賞し、翌年の二紀展で同人に推挙されます。
がしかし以降二紀会において浜口美和は同人より先に進むことはできませんでした。
二紀会での蹉跌と海外志向の始まり
武蔵野美術短期大学の卒業前なのか後なのか、いつの時点かはまだ分かっていませんが、浜口美和は当時二紀会の委員であった北村脩氏に師事しています、
その北村脩氏は二紀会創設者のひとりである宮本三郎氏に師事していたのですが、宮本三郎氏が1974年に69歳で逝去されると1976年に北村脩氏は委員から会員に戻されてしまいます。
そのため北村脩氏は1978年に二紀会を退会し、翌年一創会を設立するのですがこのあたりの詳細は『浜口美和「二紀展」出展作品集』に記載いたしましたのでご参照いただければ幸いです。
なお残念ながら、この件が起こってから後は30年以上二紀展には出品するのですが、賞を受賞することはありませんでした。
一方で宮本三郎氏が逝去した翌年の1975年に、浜口美和は一枚の繪株式会社が主催する公募展、第4回現代洋画精鋭選抜展に出品し銀賞を受賞します。
「現代洋画精鋭選抜展」は第1回(1972年)から第32回(2003年)まで毎年、第33回(2004年)は「絵の現在 精鋭選抜展」、第34回(2005年)から第39回(2010年)は「絵の現在 選抜展」で毎年、第40回は2012年で「絵の現在 選抜展」。以降は2年に1度の開催で「絵の現在 選抜展」。
さらに1976年は女流画家協会展で初めての賞となる「クサカベ賞」を受賞するのですが、その2年後に女流画家協会から退会してしまいます。
そして女流画家協会と入れ替わるようにして1976年から恐らく1991年まで欧州美術クラブが1973年から主催する「国際公募 美術賞展」[5]に出品するようになります。
[5]欧州美術クラブ「欧州美術クラブとは」 https://www.obijias.co.jp/about/
記録が残されている限りでは毎年出品するのではなく、一度出品した国で開かれる年には出品をしていないようですが、それ以外にも何かしらの理由で出品していない年があります。
このなかでジュネーブで開かれたスイス美術賞展において作品が「プチパレ美術館に収蔵]されたようです。
Googleで「プチパレ美術館収蔵」を検索すると、1977年の略歴に挙げられている作家の方々が10名近くいらっしゃいますので、皆様と同じように収蔵されたのかもしれません。
ところで話は変わりますが、一般的にはある程度名が知られた公募団体に所属している場合は、海外向け公募展がいくら入選し易いと言われていたにせよ、もしも出品して落選した場合に所属する公募団体に対してもマイナスのイメージを与えることになるので、出品には慎重になるべきことと推察致します。
それに対して浜口美和の場合には、幸か不幸かそのような縛りが緩い状況であったためにその後も様々な美術交流団体に出品を続けることになります。
このあたりの詳細につきましては「浜口美和が所属した主な海外志向美術交流団体の遍歴」にまとめてありますのでご参照いただければ幸いです。
「宇宙即我」と「万物流転」
| 年譜 | 1980年から1988年まで |
| 1980年 | 沖縄平和祈念堂美術館収蔵寄贈[F80号] |
| 1981年 | フランス美術賞展入選(於バリ) 第1回日本国際美術家協会選抜巡回展出品 ┗【会員】推挙 |
| 1982年 | 第62回朱葉会展出品【朱葉会賞】受賞 →[~2014年まで毎年出品] カナダ美術賞展出品(於トロント) |
| 1983年 | 第63回朱葉会展【会友】推挙 品川区荏原文化センター講師[~?] 第1回上野の森美術館大賞展入選 |
| 1984年 | オーストラリア美術賞展出品(於ブリスベン) 一枚の絵7月号「特集女流作家の仕事」掲載 個展(於銀座) 第2回上野の森美術館大賞展入選 |
| 1985年 | 第65回朱葉会展【会員】推挙 |
| 1986年 | 第66回朱葉会展【日航賞】受賞 第6回国際現代美術展招待出品[~1988年まで] |
| 1988年 | 第2回大田区在住作家美術展招待出品 ┗[~2016年まで毎年] 第1回アートワールド展(日本美術出版株式会社) ┗【アートワールド賞】受賞 |
1981年の沖縄平和祈念堂美術館開館に先立ち、その前年に沖縄平和祈念堂の理念に賛同する画家からの絵の寄贈を受けたのですが、浜口美和は恐らく理念のなかにある「宇宙即我」という言葉[6]に惹かれて絵を寄贈したものと思われます。
[6]公益財団法人沖縄協会「施設紹介」「美術館」 http://www.okinawakyoukai.jp/publics/index/29/
この根拠としては1979年に開催した2人展の自己紹介で「自然美に魅せられる私は人工美より、自然美を愛します。そして好きな色の青に宇宙的な広がりと、神秘を感じ幻想的思いと宇宙への畏怖への思いが重なります。」と書いているためです。
1982年から浜口美和は朱葉会展に出品を始めます。その後は2014年まで毎年出品することになるのですが、1983年を除き作品名は解っています。
浜口美和の作品名の付け方として、シリーズ名を付ける場合が多くあります。朱葉会展では全32回(内1回は調査中)の内「自然との会話」シリーズが22回、「万物流転」が2回、その他はシリーズ名を持ちながら1回しか付けられていないものや、シリーズ名を持たないのが7回となっています。
なお「自然との会話」のシリーズ名が最初に付けられたのは1989年の第69回になります。
朱葉会は1978年に退会した女流画家協会に替わる女流画家の団体で初出品で朱葉会賞を受賞し、翌年に会友、その翌々年に会員となります。
なお浜口美和の朱葉会における足跡は『浜口美和「朱葉会展」出展作品集』をご参照いただければ幸いです。
1983年に初めて開催された上野の森美術館大賞展に出品をします。翌年も出品をするのですがそれ以降は出品するのを止めてしまったようです。
基本的に浜口美和の画風は厚塗りで、どちらかというと「いまふう」ではなく、年齢としても上なので「”明日をひらく”力に満ち溢れた」というコンセプト[7]にはそぐわなかったという判断だったのかもしれません。
[7]上野の森美術館「公募展大賞展」 http://www.ueno-mori.org/exhibitions/main/taisho/
1984年に一枚の繪株式会社が発行する月刊美術誌の特集「女流作家の仕事」に、記録が残されている限りでは初めて作品が雑誌に掲載された事になります。
この時の記事の内容は現在調査中ですが、その他の掲載誌につきましては「浜口美和掲載美術誌アーカイブ」をご参照いただければ幸いです。
1985年浜口美和は朱葉会で会員に推挙されるのですが、それだけでは飽き足らないのか、1986年には国際現代美術展(i.m.a展)に招待出品します。招待の経緯は解っていませんが1988年まで、3年間出品をします。
1988年には、これも招待で第2回大田区在住作家美術展に出品をします。
大田区在住作家美術展は、その前年の1987年に大田区民プラザ開館のを記念して開催されたのですが、その翌年の1988年に大田区美術家協会が発足しています。[8]
浜口美和も大田区美術家協会に所属して2016年まで毎年出品をすることになりますが、当時接点があったか解りませんが、1997年にサロン・ブラン美術協会を設立する白尾勇次氏は大田区美術家協会発足時のメンバーの一人でした。[8]
[8]大田区美術家協会「協会の成り立ち」 http://www.ota-aa.org/m-naritachi.html
後述しますが浜口美和は2002年からサロン・ブラン美術協会に参加することになります。
この時点で、浜口美和は二紀会同人、朱葉会会員、日本国際美術家協会会員となり、1986年には朱葉会で日航賞を受賞したり、1988年には当時「藝術公論」を出版していた日本美術出版株式会社が主催した第1回アートワールド展でアートワールド賞を受賞するなど画家としてある程度のポジションを得ることができてきた時期になります。
「自然との会話」シリーズの暁光
| 年譜 | 1989年から1994年まで |
| 1989年 | 第69回朱葉会展に 『自然との会話「悠久の流れ」』を出品 |
| 1990年 | 第1回東京アートエキスポ招待出品 第5回日本の美術アートアカデミージャパン出品 ┗【トップアート賞】受賞(於パリ) 国際秀作美術展出品(於ニューヨーク) |
| 1991年 | 第71回朱葉会展【文部大臣奨励賞】受賞 第4回アートマインド大賞展【大賞】受賞 ┗(ジャパンアート社) ペルー美術賞展入選(於リマ) 日本国際美術家協会ビエンナーレ出品 ┗(於銀座セントラル美術館) |
| 1992年 | 国際公募 美展出品【大賞】受賞 ART JAPAN ’92出品(於ニューヨーク) 国際アーティストフェア出品 第4回国際美術大賞展出品【ナムラ賞】受賞 郷展出品(画廊企画) 個展(於銀座) |
| 1993年 | 国際平和美術展出品(於大阪) 第5回国際美術大賞展出品【美術評論家賞】受賞 第14回十美会展入選 国際公募 美展選抜展出品(於京都) |
| 1994年 | 国際交流美術展出品【審査員賞】受賞 ┗(於ニューヨーク) 第6回国際美術大賞展出品【東美賞】受賞 個展(於銀座) 現代の洋画掲載(マリア書房)[~2007年?] 美術の窓9月号「県別誌上ギャラリー 埼玉県」 ┗掲載((株)生活の友社) ART GRAPH11月号に掲載(アートグラフ(株)) |
1989年は浜口美和にとって「自然との会話」シリーズを始めた年であり、かつまた年齢的にも還暦に近づき画家として佳境に入る歳となります。
ただそれが少し勢いが余ってしまっていたのか、いまから見るとチャレンジし過ぎているところが散見されます。
そもそも出品したのが、国際公募展なのか?画廊企画なのか?協会なのか?会社(出版社含む)の企画なのか?判別がつかず、記録に残された名称をGoogleで検索してもほぼほぼ何も手掛かりが見つからず、結果的には出品した事への充分な効果を得ることができていないものがあることが解ります。
もっともGoogle検索でヒットしない要因としては「記録が曖昧」「検索の仕方の問題」「年代が古い」なども挙げられますが、簡単に見つけられないのであれば箸にも引っかからないという認識です。
そのような経歴は左図年譜で黄色いラインマーカーを付けたところになります。
なお資料があれば順次内容を更新して参ります。
1990年の東京アートエキスポですが1991年まで2回開催されていますが[9]、浜口美和は1回目だけの出品のようです。
[9]大日本印刷 artscape「アート・フェア」 https://artscape.jp/dictionary/modern/1198248_1637.html
1990年第5回日本の美術アートアカデミージャパンでトップアート賞、翌1991年朱葉会で文部大臣奨励賞します。
それから「アートマインド(Art mind)」という美術雑誌が1981年から2015年まで季刊で発行[10]されていたのですが、出版していた株式会社ジャパンアート社が1990年代あたりで「アートマインド秋季特別展」や「アートマインド大賞展」という名称で公募展を開催していましたが、浜口美和は1991年に「大賞」を受賞しています。
[10]国立国会図書館サーチ「アートマインド」 https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008229853-00
1992年には「国際公募 美展」に出品して「大賞」を受賞します。
「国際公募 美展」はGoogle検索でもごく僅かヒットしますが詳細は不明です。今後資料の整理が終わり次第内容は更新して行きます。
同じく1992年の「ART JAPAN ’92出品」に関しては英語で書かれたA4サイズソフトカバーの本が残されており100名以上の作家の作品が掲載されています。
なお書籍だけではなくニューヨークの「SAIREIDO Gallery」で展覧会が開催されたようなのですが、これに関してはGoogle検索で見つけることはできませんでした。
ただし1990年前後にニューヨークのSOHOに「SAIREDO Gallery」が存在していたのは確かなようですが、本に記載されている住所には現在残っていません。
ちなみにSAIREIDOの社長はNaoyuki Okada氏と書かれていて日本の方だと思います。
Naoyuki Okada氏をopencorporatesという企業のオープンデータベースで調べるとその後アメリカで4つほど会社を作られていますが、現在はすべて非活動状況です。[11]
[11]opencorporates https://opencorporates.com/officers?q=Naoyuki+Okada&utf8=%E2%9C%93
1993年の国際平和美術展は株式会社クオリアートのアートイベントになります。大阪毎日放送局内で開かれ、広島市、長崎市が後援となっています。[12]
[12](株)クオリアート「国際平和美術展」 https://www.qualiart.co.jp/works/detail.php?kijiId=20180403160125
1992年から1995年にかけて国際美術大賞展で連続して賞を受賞し、その後主催する日本選抜美術協会と合わせて常任委員の職責を拝命することになります。
1993年の十美会展は1979年に出品した「花と女性美展」を主催した十美会の開いた公募展になります。
1994年にはマリア書房の書籍「現代の洋画」に作品を掲載し、合わせて美術誌の「美術の窓」と「ART GRAPH」でも作品が掲載されることになりますが、美術誌の詳細につきましては「浜口美和掲載美術誌アーカイブ」をご参照いただければ幸いです。
結果的に浜口美和は様々な方面に出品を重ねながら「自然との会話」シリーズを醸成させて行くことになります。